炭素関連政策
質問集|一般的な炭素関連政策ツール炭素取引、炭素税、炭素料金は、気候変動に対処し、温室効果ガス排出を削減するための政策ツールです。
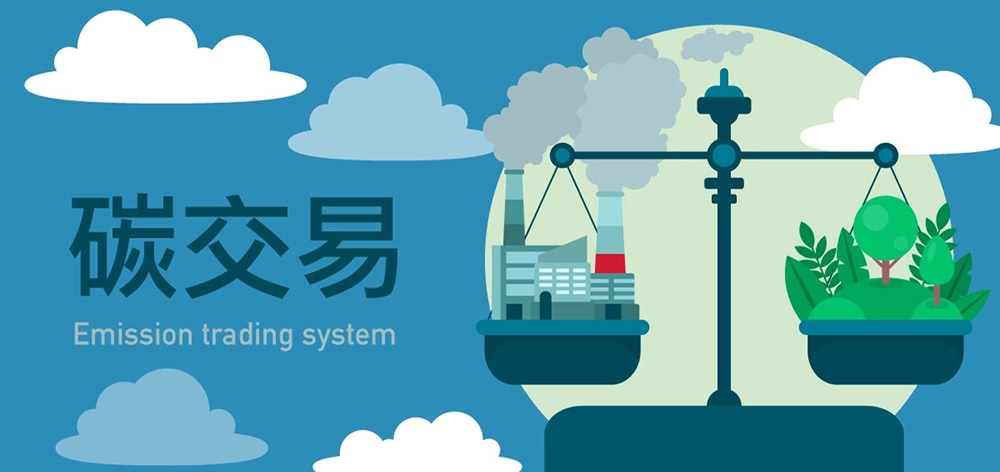
一般的な炭素関連政策ツールとは?
2027年までに先進パッケージ市場は従来のパッケージを超えると予測
環境問題と炭素関連の施策は、国家経済や国民生活に多面的な影響を与え、それらは相互に絡み合っています。例えば、高炭素排出産業への厳しい規制は、その産業の縮小や転換を引き起こし、関連企業の雇用や利益に影響を与える可能性があります。しかし同時に、これらの政策は新たなグリーン産業や技術の成長を促し、国家に新たな経済成長の機会をもたらす可能性もあります。
また、炭素関連の施策の実施には、相応の投資や資金調達が必要となります。これは政府の財政に短期的な負担をもたらす可能性があり、特に炭素削減技術、環境インフラ整備、環境教育などへの支出増加は、他の分野の投資や公共サービスの提供に影響を与える可能性があります。しかし、長期的には、これらの投資は国家の環境品質を向上させ、公害による健康問題や関連コストを削減し、国民の生活の質を向上させることに貢献します。
炭素取引、炭素税、炭素料金は、気候変動に対応し、温室効果ガス排出を削減するための政策ツールであり、以下にその概要を紹介します。
炭素取引
炭素取引(Emission Trading System、ETS)は市場ベースのアプローチであり、炭素排出権の市場を確立し、企業や国家がこの市場で炭素排出権を売買できるようにする仕組みです。各企業や国家には一定の炭素排出枠が割り当てられ、枠を超えた場合は市場で追加の排出権を購入する必要があります。一方、排出量が割り当て枠よりも少ない場合、余剰排出枠を他の必要な企業や組織に売却することができます。炭素取引を通じて、市場メカニズムによって企業がより多くの排出削減措置を講じるよう促されます。
例えば、ある国が炭素取引制度を導入し、企業に炭素排出枠を割り当てたとします。各企業は、政府から一定量の炭素排出権を受け取ります。排出枠は時間とともに徐々に減少し、企業に排出削減を促します。
企業Aと企業Bが炭素取引に参加していると仮定します。企業Aは排出量が割り当て枠を下回るため、余剰排出権を持っています。一方、企業Bは排出量が枠を超えてしまったため、追加の排出権が必要です。この場合、企業Aは余剰排出権を企業Bに売却できます。
企業Bが企業Aから排出権を購入することで、割り当て以上の排出が可能になり、企業Aは余剰排出権の売却により収益を得ることができます。この仕組みにより、企業は自社の状況に応じて、より多くの削減対策を講じるか、排出権を購入するかを選択でき、全体として炭素排出量の削減が促進されます。
炭素取引には主に2つの方式があります:「排出量キャップ&トレード方式(Cap and Trade)」と「ベースライン&クレジット方式(Baseline and Credit)」です。
排出量キャップ&トレード方式: 政府が総排出量の上限を設定し、企業ごとに排出枠を配分し、企業間で排出枠を売買可能にする仕組み。
ベースライン&クレジット方式: 総排出量に基準値を設定し、企業がその基準値を下回る排出削減を達成した場合、余剰排出削減量を取引可能な排出権として取得できる仕組み。
カーボン・オフセット
カーボン・オフセット(Carbon Offset) とは、自身の温室効果ガス排出量を相殺するために、排出削減活動を支援する方法です。通常、個人や企業がカーボン・オフセットプロジェクトに投資することで、自らの排出量を埋め合わせし、カーボン・ニュートラルまたはカーボン・バランスを実現することを目指します。
例えば、ある航空会社が新たな国際路線を開設する計画を立てたとします。この路線によって年間数千トンの二酸化炭素(CO₂)が排出されると予測されます。この排出量を埋め合わせるために、航空会社はカーボン・オフセットを購入し、風力発電や太陽光発電プロジェクトを支援できます。
航空会社は、カーボン・オフセットを管理する機関と提携し、予測されるCO₂排出量に見合ったカーボン・オフセットを購入します。この資金は、発展途上国でのクリーンエネルギー施設の建設、省エネルギー技術の導入、森林保護や植林活動などに活用されます。
カーボン・オフセットを活用することで、航空会社は自身のフライトによるCO₂排出量を相殺し、カーボン・ニュートラルを実現できます。つまり、航空会社自体は排出を続けるものの、カーボン・オフセットプロジェクトを支援することで、地球全体の排出量削減に貢献することが可能になります。
炭素料金に関する政策
炭素税:
炭素税(Carbon Tax)は、CO₂排出量に対して課税する政策手段です。企業や個人は、炭素を排出する際に一定の税金を支払う必要があり、これにより炭素排出のコストが増加します。結果として、より環境に優しいエネルギーの利用や排出削減の促進が期待されます。炭素税は、排出量に基づいて計算され、他の税収とともに政府の財政に組み込まれます。
例えば、ある工場が1,000トンのCO₂を排出した場合、政府の設定する炭素税率に基づいて、1,000 × 100 = 100,000ドルの炭素税を支払う必要があります。しかし、この工場が排出削減策を講じて排出量を800トンに抑えた場合、炭素税の支払いは80,000ドルに減少します。
このように、企業や個人は炭素税によるコストを考慮しながら、排出削減の取り組みを進めるインセンティブを得ることができます。また、よりクリーンなエネルギーの利用が促されることで、低炭素社会への移行が進みます。
炭素料金(カーボン・フィー):
炭素料金(Carbon Fee)は、炭素排出に対する課金制度であり、炭素税と類似していますが、その収益の使途が異なります。炭素税が政府の財源に組み込まれるのに対し、炭素料金は特定の環境対策に直接投資されることが多いです。例えば、再生可能エネルギー技術の開発、炭素回収・貯留(CCS)技術の研究、低炭素製品の普及促進などに活用されます。
例えば、ある工場が1,000トンのCO₂を排出した場合、政府の設定する炭素料金率に基づいて、1,000 × 100 = 100,000ドルの炭素料金を支払います。しかし、この収益は政府の一般財源には入らず、再生可能エネルギープロジェクトの推進や低炭素技術の開発支援に使われます。
炭素料金の収益を環境政策に再投資することで、さらなる炭素削減活動が促進され、社会全体の脱炭素化を後押しすることが可能になります。
カーボン・ボーダー・タックス(Carbon Border Tax):
カーボン・ボーダー・タックスは、EUが炭素漏れ(カーボン・リーケージ)を防ぎ、欧州の製造業の競争力を保護するために導入した炭素国境調整メカニズム(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)の一環です。この制度では、EU域外から輸入される製品に対して、CBAM証書を購入する形で炭素コストを支払うことが求められます。
CBAM証書の価格は、EU排出量取引制度(EU ETS)の週平均価格に基づいて計算され、EU域内の生産者が負担する炭素コストと同じ水準に設定されます。また、輸入品が生産国で炭素税や炭素料金をすでに支払っている場合、それをカーボン・ボーダー・タックスの支払い額から控除することができます。
EUではカーボン・ボーダー・タックスを段階的に導入する予定です。2026年までは、輸入業者はCBAM証書の購入は不要で、排出データの報告義務のみが課されます。しかし、2026年以降は、輸入品ごとにCBAM証書を購入し、提出する必要があります。
例えば、EUの鉄鋼業界は、炭素取引や炭素税の導入により、高額な炭素コストを負担しています。一方で、EU域外のある国の鉄鋼業は、こうした追加コストを負担せず、かつ生産過程におけるCO₂排出量もEUの鉄鋼業より高い可能性があります。
このような状況において、EUのカーボン・ボーダー・タックス制度は、この非EU国の鉄鋼製品に対して追加の炭素関税を課します。これにより、輸入鉄鋼の価格にその生産時の炭素排出コストが反映され、輸入業者が相応の炭素コストを支払う仕組みとなります。これにより、炭素漏れを防ぎ、世界的な炭素排出削減を促進し、各国がより積極的な排出削減策を取るように奨励する効果が期待されています。
カーボン・フットプリントの検証(カーボン・フットプリント・ベリフィケーション)
カーボン・フットプリント検証(Carbon Footprint Verification) とは、炭素排出データを収集し、総排出量を計算する方法です。企業はカーボン・フットプリント検証を通じて、自社の製品やサービスにおける総炭素排出量を把握することができます。
例えば、ある多国籍企業が、自社製品のカーボン・フットプリントを分析し、製造・輸送・使用の各段階における温室効果ガス(GHG)の排出量を評価するとします。これには、使用するエネルギーの種類と量、原材料の調達先、製品の輸送方法などのデータ収集と分析が含まれます。
収集したデータに基づき、第三者の検証機関が炭素排出量を計算し、カーボン・フットプリント報告書を作成します。この報告書は、さらに第三者機関による監査・検証を受け、その計算プロセスの正確性と透明性が確認されます。最終的に、企業はこの報告書を活用し、製品の環境影響を消費者、投資家、規制当局に対して説明し、気候変動対策への取り組みを示すことができます。また、排出削減戦略を立案し、カーボン・フットプリントの改善を図るための指標として活用することも可能です。
環境保護庁(EPA)や国際標準化機構(ISO)が推奨するカーボン・フットプリント検証基準として、温室効果ガス排出量検証ガイドライン(GHG Protocol)やISO 14064-1:2018 があります。
さらに、環境省が指定した特定の産業や高排出企業だけでなく、一般企業でもカーボン・フットプリント検証を実施することが可能です。カーボン・フットプリント検証は、企業が総炭素排出量を明確にし、脱炭素戦略を策定するための基盤として活用されます。これにより、企業はカーボン・ニュートラルの推進や、グローバル企業が求めるサプライチェーンの環境要件への適合を進めることができます。
エネルギー管理と脱炭素を同時に実現?
EMS スマート電力管理システム
企業はますます、製造プロセスにおいてカーボンニュートラルや排出削減の目標を達成することを求められています。これは、持続可能な発展への取り組みを支援するためのものです。効果的な電力管理は、サステナブルな生産目標を実現するための重要な要素となります。
スマート電力管理システム


